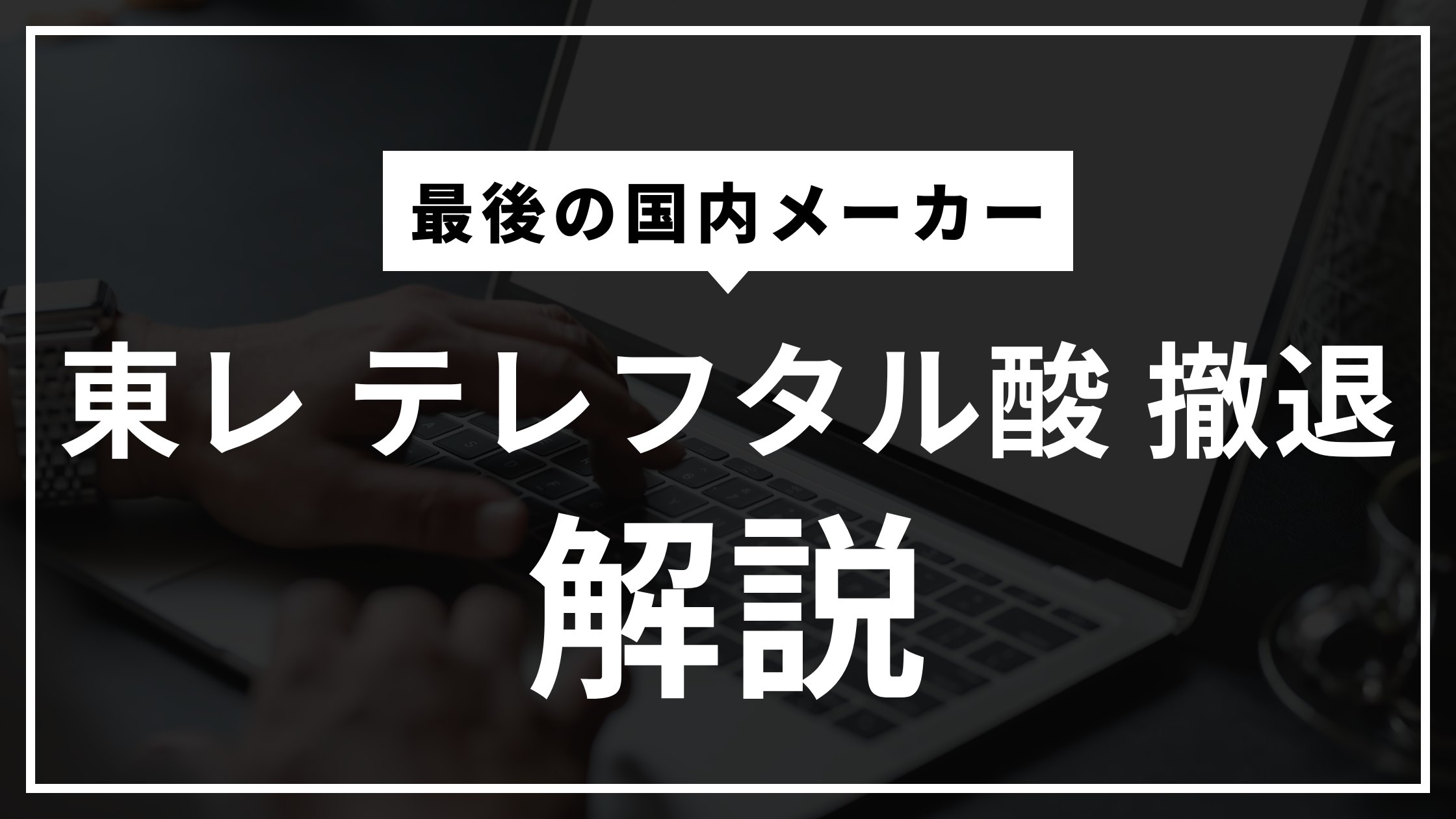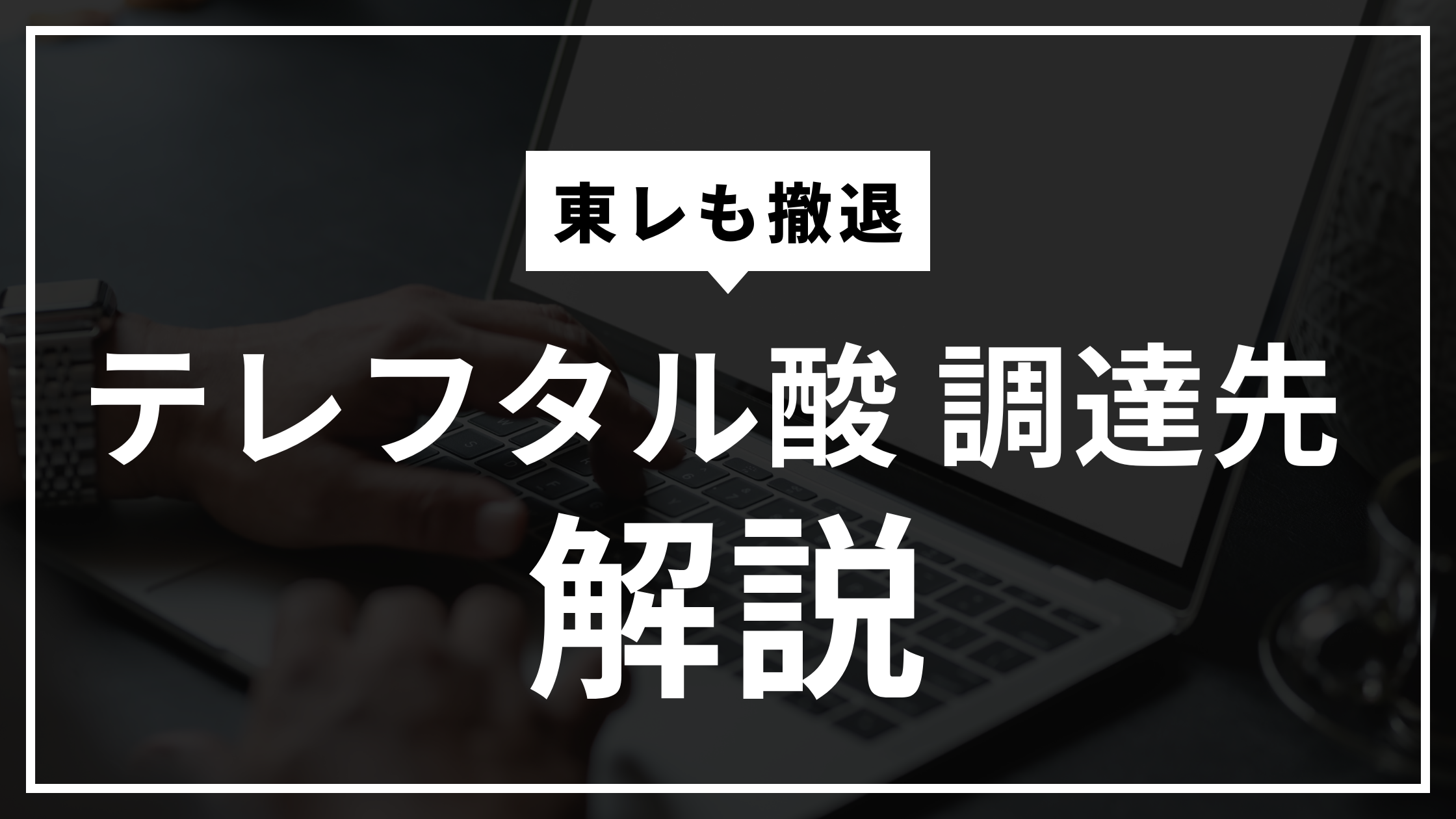アセンド破産が映すナイロン業界の構造転換:依存リスクの現実
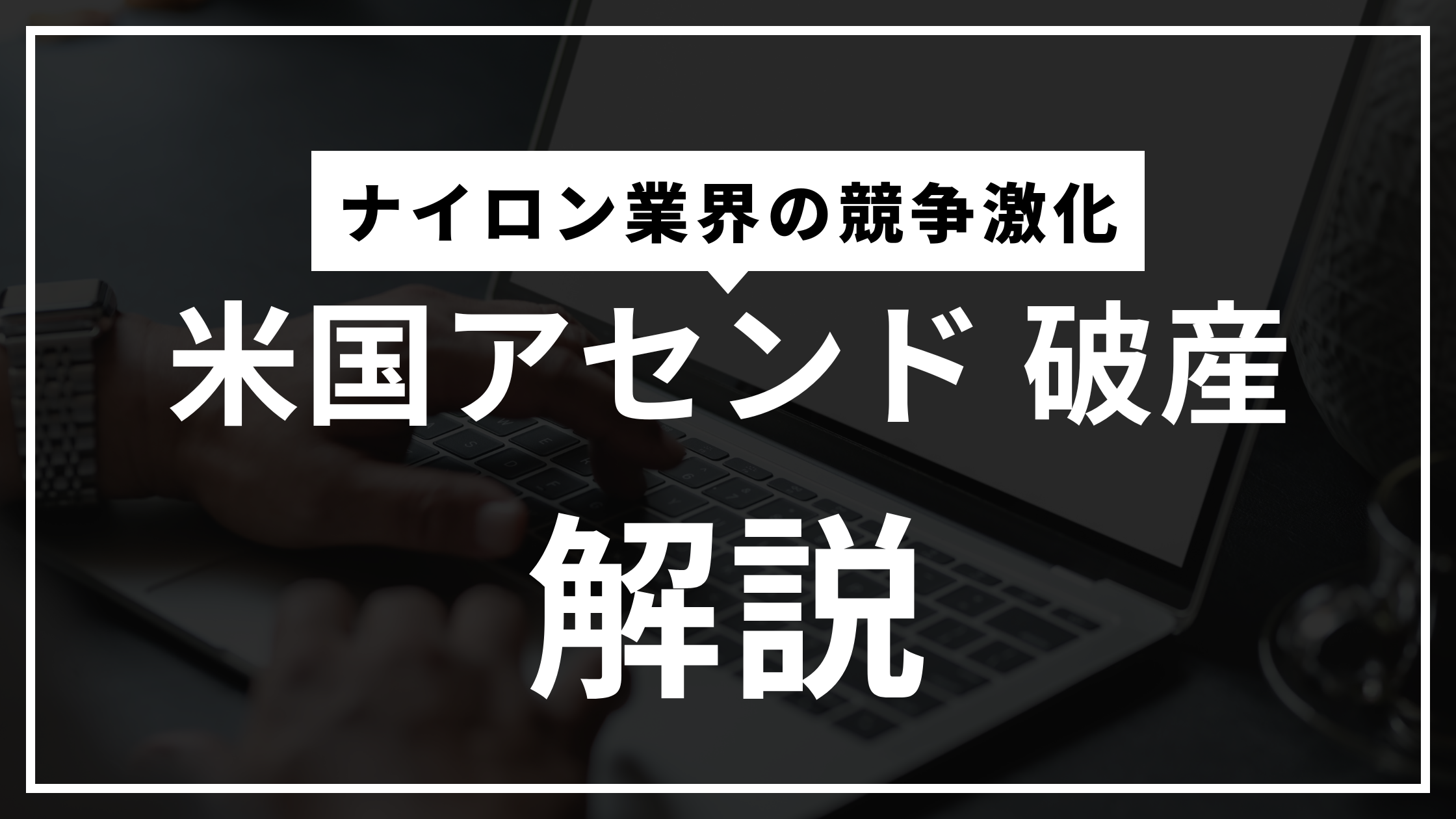
1. 導入:アセンド破産が突きつけた現実
2025年4月21日、アセンド・パフォーマンス・マテリアルズは、米国テキサス州南部地区連邦破産裁判所に米連邦破産法第11章(Chapter 11)の適用を申請した。ナイロン66の主要原料であるヘキサメチレンジアミン(HMDA)において世界最大級の生産能力を誇る同社の破綻は、ナイロン業界全体に衝撃を与えている。
アセンドは、もともと米デュポン社の化学品部門から分離・独立する形で2009年に設立された企業であり、ナイロン66のバリューチェーン全体をカバーする数少ないプレーヤーとして急成長を遂げてきた。特に、ヘキサメチレンジアミン(HMDA)やアジピン酸(AA)などの中間体を自社で一貫製造できる強みを活かし、自動車・電気電子・消費財分野向けにグローバル展開を進めていた。2020年代に入り、アジア(特に中国)市場の成長性を見据え、中国江蘇省連雲港に新工場を建設するなど、グローバルな生産体制の強化にも乗り出していた。
しかしその矢先に起きた破産劇は、単なる資金繰りの失敗ではなく、業界構造全体が抱える脆弱性を象徴する出来事である。供給過剰、地政学リスク、環境規制といった多層的な課題が絡み合う中、サプライチェーン全体が再構築を迫られている。ナイロン業界におけるこの「異変」は、今後の市場再編の前触れにすぎない可能性がある。
2. 背景:破産に至るまでの流れ
2.1 コロナ禍後の需要回復と過剰投資
COVID-19のパンデミックからの回復に伴い、自動車や電子機器市場が急速に需要を取り戻したことで、ナイロン66の原料需要も急増した。ナイロン66は、自動車(エンジン周り、冷却系)、電気・電子部品(コネクタ、リレー)などに広く使われており、とくにEVの普及により高温部材や軽量化部品としての需要が拡大すると予測されていた。
各国の企業は、こうした市場の動向に対応すべく大規模な生産設備投資を開始。アセンドも例外ではなく、中国江蘇省連雲港市にHMDAおよび特殊化学品の新工場を建設するなど、積極的な設備投資を進めていた。
さらに、米中貿易摩擦や地政学的リスクの高まりにより、各国が自国および地域内のサプライチェーン強化を掲げるようになっていた。アセンドの中国投資は、アジア市場への供給体制の構築のみならず、サプライチェーンの地域分散化を図る戦略的な動きでもあった。自動車や電子機器市場が急速に需要を取り戻したことで、ナイロン66の原料需要も急増した。各国の企業は、これに対応すべく大規模な生産設備投資を開始。アセンドも例外ではなく、中国江蘇省連雲港市にHMDAおよび特殊化学品の新工場を建設するなど、積極的な設備投資を進めていた。
2.2 中国企業の台頭と供給過剰
中国国内では政府の補助金を背景に、化学品メーカーがナイロン66の中間体であるアジポニトリル(ADN)やHMDAの生産能力を急拡大。2020年代前半の数年間で、ADNの生産能力は前年比93%増、HMDAも64%以上増加したと報告されている。こうした供給過剰は、世界市場における価格競争を激化させ、アセンドのような高コスト体質のメーカーにとって収益を圧迫する要因となった。
中国政府が補助金を出す背景には、戦略的新興産業の国産化を推進する「中国製造2025(Made in China 2025)」政策がある。特に化学工業分野においては、高付加価値の中間原料を自国で製造可能にすることで、サプライチェーンの自立性を高め、国際競争力の強化を図っている。ナイロン66は、自動車・電子機器・繊維といった基幹産業の素材として位置づけられており、同国内での安定供給体制の確立は経済安全保障上の観点からも優先度が高いと判断されている。
2.3 米国国内コストの高騰と外的要因
米国内では、エネルギー価格の高騰、労働力不足、インフラ老朽化による物流遅延が重なり、製造業全体のコスト構造が悪化していた。アセンドはナイロン66の中間体をアラバマ州やフロリダ州で生産しており、これらの拠点にかかる運転コストの増加が企業財務に深刻な影響を与えていた。
アセンドはナイロン66の中間体をアラバマ州デカター、フロリダ州ペンサコーラ(カントンメント)、テキサス州チョコレート・バイユー(アルビン)といった複数の工場で分散製造していたが、これらの工場間は数百キロメートル以上離れており、原料や中間体の輸送には主にトラックや鉄道が使用されていた。
特にデカター工場からの中間原料はパイプライン接続がなく、水運にも制約があるため、長距離かつ非効率な輸送ルートを経由せざるを得なかった。2025年前半には、アラバマ州からの原料輸送に使用されていたウィルソン・ロック(水門施設)の閉鎖により、水運ルートが遮断され、トラック輸送に全面的に切り替える事態となった。この結果、2025年第1・第2四半期だけで800万ドル以上の追加物流費が発生し、製品原価の上昇が避けられなかった。
一方で、チョコレート・バイユー工場では、テキサス州テキサスシティのイーストマン・ケミカルズ工場との間に約37キロメートルの液体パイプラインが敷設されており、アンモニアやプロピレンなどの原料輸送に使用されている。このようなパイプラインの存在は、輸送効率を高め、コスト削減に寄与しているが、アセンド全体の物流構造としては地理的な分散と輸送インフラの制約が製造コストを押し上げる要因となっていた。
2.4 自然災害と操業停止
2024年12月、フロリダ州ペンサコーラにあるアセンドの主力ナイロン製造工場で大規模な火災が発生した。この火災は、複数階建ての操業ユニットで発生し、数マイル先からも厚い黒煙が確認されるほどの規模だった。負傷者はなかったが、2025年2月中旬まで操業停止となり、約600万ドルのEBITDA損失を計上した。
翌2025年1月には、テキサス州を襲った記録的な寒波により、同州チョコレート・バイユー工場が操業停止を余儀なくされた。ここで製造されるアセトニトリル(ACN)やシアン化水素(HCN)はアラバマ州デカター工場にも供給されており、寒波による停止は他拠点にも影響を与えた。ACNは外部からプレミアム価格で緊急調達され、コストが大幅に上昇した。
これらの災害に加え、アラバマ州でウィルソン・ロックの閉鎖が発生。水運が遮断され、物流費が800万ドル以上増加した。これら複合的な要因により、2025年第1四半期のEBITDAは2,100万ドル減少し、破産申請の決定的要因となった。
2.5 資金繰り悪化と破産申請
これらの複合的要因が重なり、2025年初頭には支払遅延の累積額が1億1,000万ドルを超えた。取引先からの前払い要求や供給停止のリスクが高まり、アセンドはDIPファイナンスにより運転資金を確保したうえで、Chapter 11の適用を選択した。
ここで留意すべきは、アセンドが選択した「Chapter 11(チャプター・イレブン)」が、単なる倒産(清算)とは異なる点である。Chapter 11とは米連邦破産法第11章に基づく事業再建手続きであり、操業を継続しながら債務の整理や資本構成の再構築を目指す制度である。
「倒産」という言葉が日本では即「会社が潰れる」ことを意味しがちだが、Chapter 11はむしろ再起のための法的枠組みであり、経営陣が引き続き指揮を執ることが可能である(DIP制度)。
アセンドは、高付加価値の技術資産やグローバル顧客基盤を有しており、完全清算よりも事業を継続した方が全体の価値が維持されると判断したと見られる。Chapter 11の選択は、再建のための戦略的判断であり、取引先・従業員・顧客との関係維持を最優先した意思決定だったといえる。支払遅延の累積額が1億1,000万ドルを超えた。取引先からの前払い要求や供給停止のリスクが高まり、アセンドはDIPファイナンスにより運転資金を確保したうえで、Chapter 11の適用を選択した。
3. 分析:アセンド破産の真因
3.1 構造的な供給過剰と価格崩壊
2020年代に入ってからの中国勢の攻勢により、ナイロン66原料市場は深刻な供給過剰状態に陥っていた。市況は低迷し続け、アセンドのような米系企業は採算ラインを下回る価格でも競争を強いられた。高純度・高品質を売りにしていた同社にとっては、価格競争への対応が難しかった。
中国企業のナイロン66市場への参入は、国家戦略に基づく明確な方針の下で進められてきた。中国政府は、ナイロン66の主要原料であるアジポニトリル(ADN)やヘキサメチレンジアミン(HMDA)の国産化を「中国製造2025」に基づき重要産業と位置づけ、補助金や優遇税制を通じて企業の参入を促してきた。
例えば、Longhua New Material社は山東省淄博市に年産108万トンのナイロン66一貫製造プラントを建設中で、2028年稼働を目指している。こうした大型案件が複数進行しており、中国国内の生産能力は2025年までに年産200〜250万トン規模に達する見込みである。
一方で、2023年の中国国内のナイロン66消費量は52万4,000トンにとどまっており、生産過剰の構造が顕在化している。加えて、ADNの新設も進み、2024年だけで20万トンの能力が追加される予定であり、原料段階でも供給過剰が深刻化している。
このような過剰供給の状況は、グローバル市場全体の価格を押し下げ、高コスト構造の欧米メーカーにとって大きな収益圧迫要因となっている。アセンドのように垂直統合型のモデルを持つ企業ですら、この構造的な価格下落には耐えきれず、経営を圧迫されるに至った。
3.2 経営資源の集中とリスク分散不足
【図1】ナイロン66の垂直統合バリューチェーン
アジポニトリル(ADN)
↓水素化
ヘキサメチレンジアミン(HMDA)
+
アジピン酸(AA)
↓縮合重合
ナイロン66ポリマー
↓
用途別グレード(自動車・電子部品・医療など)
ナイロン66の主原料は、ヘキサメチレンジアミン(HMDA)とアジピン酸(AA)という2つのモノマーである。HMDAはアジポニトリル(ADN)から水素添加によって製造されるが、このプロセスには高圧水素ガス、ニッケル系触媒、高温反応といった高い技術と設備が必要であり、新規参入障壁が高い。AAは主にシクロヘキサンの酸化によって製造され、副生成物として強力な温室効果ガスであるN₂O(一酸化二窒素)を排出する。この環境負荷が、特に欧州系メーカーの製造コストに大きく影響している。
アセンドやインビスタは、これらの中間体からナイロン66樹脂までを自社内で製造する垂直統合型モデルを採用している。このモデルの利点は、(1)原料価格の変動影響を受けにくい、(2)製品の品質を全工程で一貫して管理できる、(3)顧客ニーズに応じたグレード設計が容易、(4)供給安定性に優れる、などが挙げられる。とくに自動車・電気電子分野では、こうした安定性と品質の高さが強く求められるため、アセンドは競争優位を築いてきた。
しかし、垂直統合は巨額の設備投資と固定費を伴うため、市況悪化や需給の緩みが発生すると採算が悪化しやすい。また、災害や設備トラブルが一拠点に発生すれば、上流から下流まで波及する構造的リスクも抱えている。実際にアセンドは、2024年末の火災と2025年の寒波により、生産チェーン全体が麻痺し、事業継続性に大きな打撃を受けた。
一方、中国ローカルメーカーは、原料を外部調達することで設備投資負担を抑えつつ、低価格を武器に市場を急拡大している。こうした企業との価格競争において、アセンドのような高コスト構造の企業は不利を強いられ、結果としてグローバル競争力の低下が避けられなかった。
3.3 財務の柔軟性欠如
供給価格の下落や操業停止によって短期キャッシュフローが悪化した際、迅速に外部資金を調達し対応する仕組みが構築されていなかった。破綻前の段階でブリッジローン(短期つなぎ融資)や緊急融資を得ていたものの、根本的な資本再編には至らなかった。
ブリッジローンとは、本格的な資金調達(たとえば長期融資や増資)が完了するまでの“橋渡し”として借り入れる短期融資のことで、通常は金利が高く、返済猶予も短い。
この手法によりアセンドは、設備復旧や仕入れ支払いといった緊急キャッシュニーズを一時的に乗り切ったが、抜本的な資本構造改革には至らなかった。むしろ、財務コストの上昇が経営をさらに圧迫し、最終的にはChapter 11申請を選ばざるを得ない状況に追い込まれたと考えられる。
4. 業界への影響:ナイロン業界の地殻変動
4.1 サプライチェーンへの影響と混乱
アセンドはナイロン66およびその中間体であるアジピン酸(AA)やヘキサメチレンジアミン(HMDA)の主要サプライヤーであり、同社の供給停止はグローバルなナイロン66バリューチェーンに直接的な影響を与える。
とくに影響を受けるのは以下のようなユーザー層である:
- ナイロン66樹脂を使用する自動車部品、電気・電子部品、工業製品の成形メーカー
- アジピン酸・HMDAを中間原料として使用するナイロン66樹脂メーカーやポリウレタン原料メーカー
- 特定グレードのナイロン66に対して材料認証を取得済みの企業(例:UL認証、OEM指定)
- 原料の調達先としてアセンドに大きく依存していた中堅〜中小のコンパウンド加工メーカー
これらの企業では、材料供給の遅延、品質要件を満たす代替品の不足、再認証の負担、原料価格の高騰といった問題に直面しており、調達・製造・販売の各フェーズで計画の見直しが迫られている。
アセンドの破産は、単なる一企業の経営問題ではなく、グローバルなサプライチェーンにおける依存構造の脆弱性を露呈させたと言える。
4.2 他の大手メーカーの対応
【図2】主要プレイヤーの構造比較
| 企業名 | 垂直統合度 | 主力製品 | 強み | 弱み |
|---|---|---|---|---|
| アセンド | 高 | HMDA〜ナイロン66 | 技術力・品質管理力 | コスト高・自然災害脆弱性 |
| インビスタ | 高 | ADN〜ナイロン66 | ADN供給力・中国拠点 | OEM依存度が高い |
| BASF | 中 | AA〜ナイロン樹脂 | グローバル供給体制 | 統合度は限定的 |
| 中国ローカル | 低〜中 | 最終品・樹脂 | 価格競争力・成長性 | 品質・安定性への懸念 |
インビスタ(INVISTA)やBASFといった他の主要プレーヤーは、アセンドの供給不安を受けて、短期的な供給調整や新規顧客対応を迫られている。
インビスタは、中国においてADNやHMDAの一貫生産体制を構築しており、アセンドの代替供給先として注目されている。また、BASFはグローバルな生産拠点ネットワークを活かし、地域間での製品供給調整を進めている。
ただし、いずれの企業にとっても、急激な需要シフトや顧客ごとの仕様対応には限界があり、全体として供給不安定な状況が続く可能性が高い。
4.3 中国ローカル企業の台頭
アセンドの破産と欧米大手の供給制約を受けて、中国ローカルメーカー(例:Shandong Haili、Longhua New Materialなど)は、アジアを中心に積極的な市場拡大を進めている。
これらの企業は政府の支援の下で価格競争力を高めており、欧米日系メーカーの調達先として浮上しつつある。ただし、品質保証、グレード安定性、環境規制対応などの観点から、慎重な見極めが求められている。
アセンドの供給不安を契機に、グローバルナイロン66市場における勢力図の変化が加速しているのは間違いない。
5. 迫る試練:ナイロン業界が直面する3つのリスク
5.1 長期化する価格競争
中国企業の参入によって引き起こされた原料および樹脂の供給過剰は、今後も継続する可能性が高い。中国国内でのADN・HMDA・ナイロン66の一貫製造設備の新増設が相次いでおり、2025年以降も世界市場への輸出圧力は強まり続けると見られている。
このような構造的な価格競争の長期化は、欧米・日系メーカーにとって収益性の低下を意味する。垂直統合型の高コスト構造を持つプレーヤーほど厳しい戦いを強いられ、リストラや事業売却の加速が懸念される。
供給過剰が続く理由
中国における供給過剰が今後も継続すると見られる背景には、以下の要因がある。第一に、既に稼働が予定されている大型設備が多数存在する点である。たとえばLonghua New Material社は、2028年に稼働予定の年産108万トンの一貫製造ラインを建設中であり、その他の企業も同様の投資を進めている。
第二に、これらの設備は中国国内の内需(2023年時点で約52万トン)を大きく上回る生産能力を持ち、輸出前提の計画となっている。これにより、グローバル市場に対して恒常的な供給圧力がかかる構図となる。
第三に、中国政府は「中国製造2025」や「双炭政策(炭素排出ピーク・カーボンニュートラル)」の方針の下で、化学品の国産化や生産支援に注力しており、補助金制度などが継続的に適用されている。採算性よりも国家戦略を重視した投資判断が行われることで、需給バランスの是正が遅れる要因となっている。
5.2 環境対応コストの増加
ESGとは、環境(Environmental)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの観点から企業を評価する考え方であり、近年では調達・投資・融資の判断基準として急速に浸透している。とくに欧州では、温室効果ガス排出規制、再生可能資源使用義務、製品ライフサイクル評価(LCA)といった高度な環境対応が求められており、それに応じた技術開発と投資が避けられない。
ナイロン66の原料であるアジピン酸の製造では、一酸化二窒素(N₂O)が副生成される。この温室効果ガスへの対応には専用の除害装置やプロセス改善投資が必要であり、欧米メーカーはすでに多額の設備改修を行っている。一方、中国企業も将来的には同様の環境規制に直面するが、現時点では猶予期間や運用面の緩さから比較的低コストで生産が可能である。
また、欧米企業はESGスコアの維持が資本市場や顧客評価に直結しており、環境・社会・統治全体にわたる企業統治コストが高い。これに対し、中国ローカル企業は短期的な採算性を重視し、環境対応において競争上のアドバンテージを維持している構図となっている。
欧州を中心に、温室効果ガス排出や再生可能資源の使用比率に関する規制強化が進んでおり、ナイロン業界にも強いESG対応が求められている。アジピン酸の製造過程で排出されるN₂Oへの対策技術や、バイオ由来ナイロンの開発・量産化には大規模な投資が必要だが、それに対応できる企業は限定されている。
ESG格付けが調達や融資条件に影響するようになりつつある今、環境対応の遅れは企業価値に直結するリスクとして捉える必要がある。
5.3 地政学的リスクの拡大
米中対立、ロシア・ウクライナ戦争、台湾海峡の緊張など、世界各地での地政学リスクが高まる中、化学品のサプライチェーンはかつてない不確実性に直面している。
中国に原料調達や加工工程を依存する企業は、調達コストの変動や規制リスクに常にさらされることになる。今後、各企業は「どこでつくり、どこで売るか」を地政学と物流の観点から再設計しなければならない。
地政学的リスクを逆手に取り、供給網を最適化している先進企業の戦略にも注目が集まっている。
- **LG Chem(韓国)**は、米中対立を想定し、EVバッテリー材料や高機能樹脂の供給において“デュアルサプライチェーン”戦略を導入。中国市場と米国・欧州市場で生産拠点・原料・認証を完全に分離し、制裁や規制の影響を最小化。
- **SABIC(サウジアラビア)**は、日本のイノアックと合弁でSABIC イノアック コリアを設立。中東の資源と日本の加工技術を融合し、アジア地域での分散供給体制を強化。
- **BASF(ドイツ)**は、欧州・北米・中国に統合型のヴェルブント拠点を分散配置。湛江(中国)拠点は現地完結型とし、欧州とは政治・物流リスクを切り離して運用。ロシア・ウクライナ戦争後には欧州のガス依存を下げる柔軟対応を実施。
これらの企業に共通するのは、政治リスクを前提とした柔軟な供給構造の構築であり、今後の化学業界においては“地政学回避型戦略”が競争力の鍵となるだろう。
6. 企業が取るべきアクション
6.1 調達戦略の再構築
アセンドの破産は、特定サプライヤーや特定地域への依存が持つ危険性を明確に示した。今後は、地域・供給元の分散化(マルチソーシング)や在庫管理の見直し、バックアップ調達ルートの確保が不可欠である。
調達先の評価基準も、価格のみならず、供給安定性・環境対応・認証取得状況など、多面的な基準に基づくものへと進化させる必要がある。
6.2 高付加価値化と用途特化の推進
汎用品としてのナイロン66は今後も価格競争が続くと見られるが、一方で耐熱性、耐薬品性、難燃性などの機能性を強化した製品群へのニーズは高まっている。用途特化型のグレード開発を進め、他社との差別化を図ることが収益性確保の鍵となる。
特にEV、5G、医療、宇宙・航空といった分野での応用を視野に入れた製品開発が求められる。
6.3 中国依存度の最適化
中国市場は今後も成長が期待されるが、すべてを中国に依存するのは大きなリスクを伴う。製造拠点・原料調達・販売網について、グローバル分散型の体制を整備することが望ましい。
また、中国企業との関係性も「一方的な依存」ではなく、共同開発・現地合弁・技術提携といった双方向の戦略関係へと進化させるべき時期に来ている。
なお、中国パートナーとの協業においては、持続的かつ健全な関係を築くためのリスクマネジメントも不可欠である。これは特定の国に限らず、国際的な事業連携において普遍的な課題といえる。
たとえば契約面では、知的財産や供給義務、品質基準などを明確にした詳細な契約を締結し、万一の紛争に備えて国際仲裁機関(例:シンガポール、香港)での解決を可能とする条項を盛り込むことが推奨される。
運用面では、コア技術のブラックボックス化や段階的な技術移転、R&Dや品質保証機能の自社保持といった措置を講じることで、依存度を抑えつつ協業を進められる。また、ASEANやインドなど他地域での供給基盤構築も併行すれば、環境変化への対応力が高まる。
こうした慎重かつ戦略的な設計により、信頼関係を損なうことなく、柔軟で安定した国際パートナーシップを形成することができる。
7. 結論:ナイロン業界再編時代の始まり
アセンドの破産は、単なる一企業の経営破綻にとどまらず、ナイロン66市場の構造的転換を象徴する出来事である。インビスタ、BASF、LG Chem、SABICといった主要プレーヤーは、それぞれ異なる戦略でこの変化に適応しようとしている。
たとえば、インビスタはADN供給力を軸にOEM主導の市場戦略を展開し、BASFは欧州・中国・北米に分散したヴェルブント型拠点を通じてリスク分散を図っている。LG Chemは米中分断を想定し、地域ごとに供給網・認証・原料を分けた“デュアルサプライチェーン”戦略を確立。SABICは中東の原料優位性と日系技術を融合させた合弁モデル(SABIC-イノアク・コリア)を通じ、アジア市場の安定供給を実現している。
こうした中で、従来の垂直統合モデルの限界が明らかになりつつある。今後のナイロン業界では、調達・生産・販売の全体設計を地政学と環境変化を前提に再構築する必要がある。アセンドの教訓は、「変化への遅れ」が致命傷になりうる時代への警鐘といえるだろう。